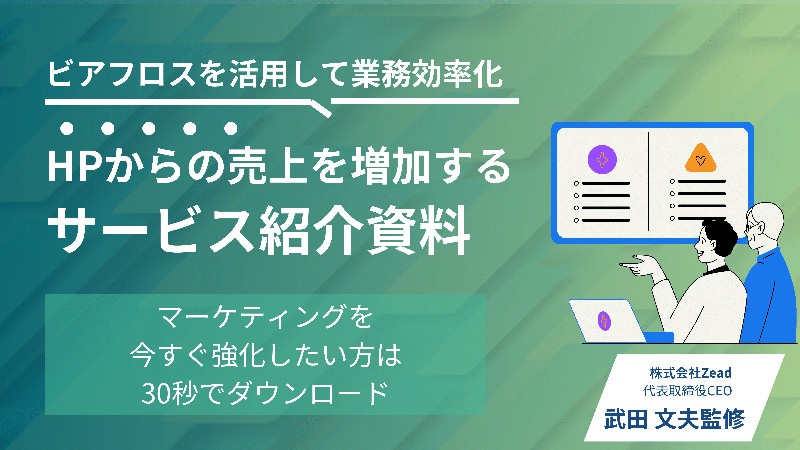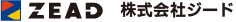インサイドセールスはやめとけと言われる理由は?向いていない人の特徴と対策
2025.3.11本記事では、インサイドセールスが「やめとけ」と言われる理由や、向いている企業・向いていない企業の特徴、成果を出すためにどのような工夫をすべきか詳しく解説します。インサイドセールスの導入を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
インサイドセールスが「やめとけ」と言われる理由

インサイドセールスは現在、営業活動の効率化や売上向上に貢献する手法として大きな注目を集めています。しかし、一部では「やめとけ」と言われている事も事実です。では、なぜそのように言われるのか解説します。
対応する顧客数が多い
まずインサイドセールスを導入した場合、自ずと一日に対応しなければならない顧客数が多くなります。インサイドセールスはフィールドセールス(外勤営業)と異なり、電話やメール、オンライン上での商談が主となります。短時間で多くのリードにアプローチできるのが大きな利点ですが、その分短期間で成果を求められるため、業務負担が大きくなるケースも少なくありません。
特に、見込み顧客の温度感が低い場合は何度もアプローチして関係を構築する必要があります。そのため、1日に何十件もの連絡をこなすことになり、業務が単調になりがちです。さらに、成果が出るまでの時間が長引くとモチベーションの維持が難しくなり、離職率が高くなる可能性もあります。
顧客との信頼関係を構築するのに時間がかかる
顧客と直接対面する機会が少ないため、信頼関係の構築が難しいとされています。フィールドセールスでは直接顔を合わせてコミュニケーションを取ることで関係を深めやすいですが、インサイドセールスでは電話やメールなど非対面での対応が中心となるので、どうしても顧客の本音を引き出しにくいです。
特に、顧客がすでに他社と関係性を築いていた場合、オンライン上のやり取りだけでは信用を得るのに時間がかかります。また、メールや電話では相手の反応を細かく確認ができず、温度感の見極めが難しくなるため、成約までのプロセスが長引くケースもあります。
そのため、単純な営業トークをするだけでなく、顧客の課題を深く理解し、顧客それぞれに対する適切な解決策の提案が必要不可欠です。この点を理解していないと成果が出にくく、ストレスを感じる要因にもなるでしょう。
各部門の板挟みになる
さらにインサイドセールスを行う社員は営業チームの一員でありつつも、マーケティングチームやフィールドセールスとも連携しながら業務を進める必要があります。そのため、各部門の意向を調整する立場になりやすく、板挟みになってしまうかもしれません。
まず、マーケティングチームが獲得したリードの質に問題があれば、インサイドセールスの業務負担が増します。一方で、フィールドセールスが求めるレベルの顧客を送り出せていなければ、成果が上がらない、と指摘を受ける可能性もあります。こうした状況が続くと、自分ではコントロールできない部分で評価が左右されるため、フラストレーションが溜まりやすいです。
さらに、組織の方針変更によって業務の方向性が頻繁に変わると対応がより難しくなります。急な戦略転換でターゲット層が変わると、それまでのアプローチ方法が通用しなくなり、これまで通りの成果すら出しにくくなります。こうした環境の変化に柔軟に対応できないと、ストレスを感じやすくなるでしょう。
インサイドセールスの仕事内容
インサイドセールスは、非対面で営業活動を行う手法として多くの企業で導入されています。顧客との対面を前提とするフィールドセールスとは異なり、電話やメール、オンライン商談を活用して、顧客の獲得、育成や商談の創出、関係性構築など幅広い業務を行います。特に、マーケティングチームが獲得したリードにアプローチし、適切なタイミングでフィールドセールスへ引き継ぐ役割も担うのが特徴です。
業務の中心となるのは、見込み客とのコミュニケーションです。まず、問い合わせ対応やリードリストを基にしたアプローチを行い、顧客の興味・関心を把握します。その上で、課題やニーズをヒアリングし、最適な提案ができるように関係を構築していきます。特にBtoBの分野では購買プロセスが長期化するため、定期的なフォローを行いながら信頼関係を築くことが求められます。
また、インサイドセールスは単なる営業活動にとどまらず、データ分析や営業プロセスの最適化にも関与します。SFA(営業支援ツール)やCRM(顧客管理システム)のようなツールを活用して顧客情報や商談の進捗状況を管理し、成果を最大化するための戦略を立てることも大切な業務の一つです。こうしたデータに基づくアプローチによって効率的な営業活動を実現し、売上向上に結びつける仕事でもあります。
インサイドセールスはやめとけ?導入する3つのメリット
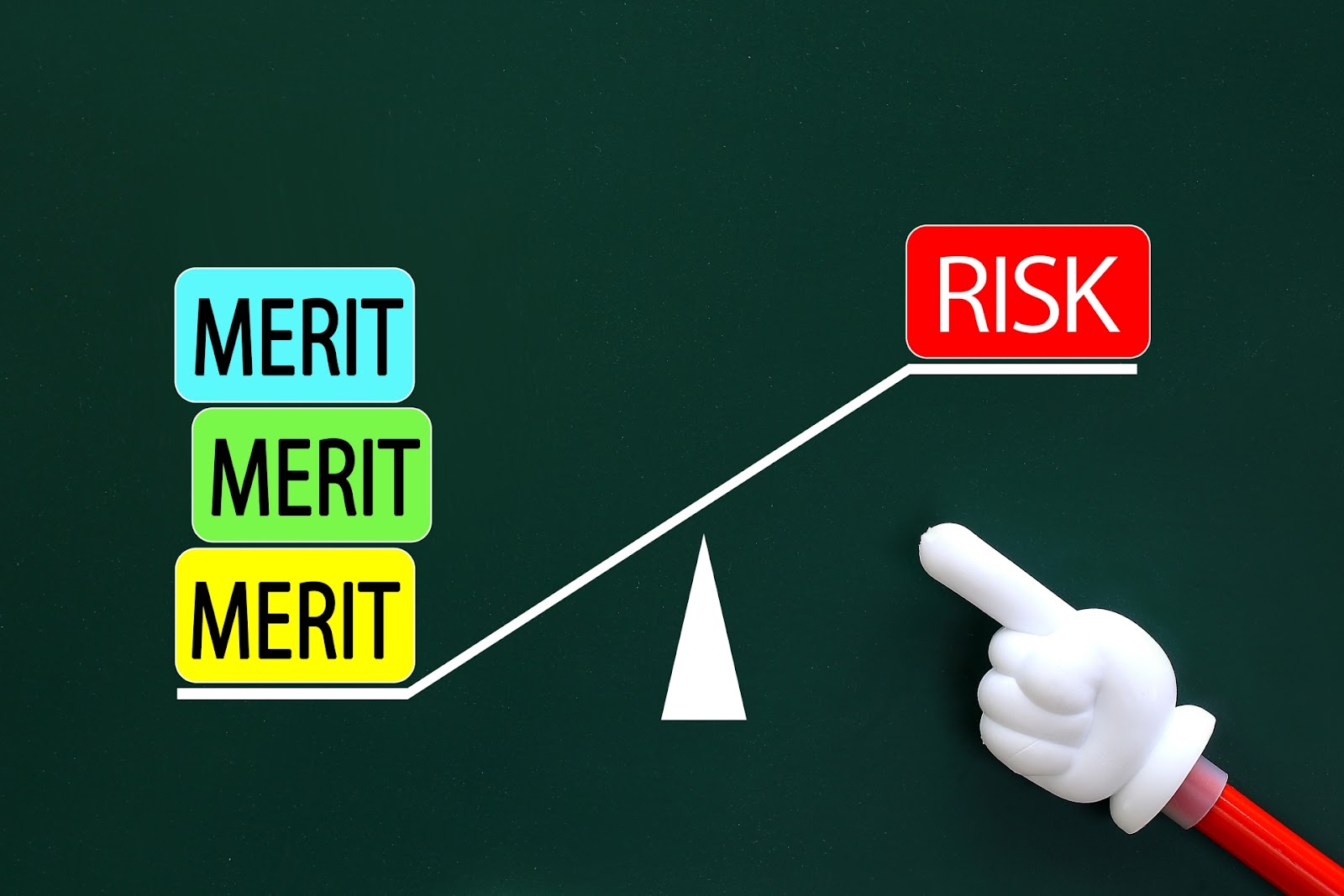
先ほどお話した通り、インサイドセールスの導入には一定のリスクが伴うため、「やめとけ」と言われています。しかし、多くの企業が導入し、成果を上げているのも事実です。非対面での営業活動だからこそ得られるメリットがあり、適切に活用すれば業績向上につながる可能性は大いにあります。それでは、インサイドセールスの導入で得られる3つのメリットを紹介します。
安定した売上の確保
インサイドセールスの導入は、安定した売上の確保に大きく貢献します。非対面での営業活動により営業担当者は移動時間の大幅な削減が可能となり、より多くの見込み客に効率的にアプローチできます。これにより定期的なフォローアップが容易になり、顧客との長期的な関係構築が促進されます。結果として、継続的な収益基盤の強化が期待できるでしょう。
業務の属人化回避
フィールドセールスを導入した場合、特定の担当者のスキルや人脈に依存するケースが多く、担当者が退職する際に引き継ぎが難しくなる可能性も少なくありません。
しかし、インサイドセールスはデータを元にした営業手法であり、顧客情報や商談履歴をチームで管理できるため、属人化を防げます。これにより、業務の標準化が進み、組織全体の営業力を向上させることができます。
1日にアプローチできる数が多い
フィールドセールスでは1日に対応できる顧客数が限られますが、インサイドセールスは電話やメール、オンライン商談がメインなので、1日あたりの商談数を増やし、成約のチャンスを拡大できます。さらに、マーケティング施策と組み合わせればより多くの見込み顧客を効率的にフォローできる点も魅力です。
インサイドセールスに向いていない企業の特徴とは?
インサイドセールスは多くの企業にとって効率的な営業手法となり得ますが、すべてのビジネスに適しているわけではありません。特に、ターゲット層や商品特性、事業方針によっては、インサイドセールスの導入が効果を発揮しにくいケースもあります。ここでは、インサイドセールスに向いていない企業の特徴を解説します。
ターゲット層が限られている
ターゲットとなる顧客層が狭い場合、見込み顧客の母数も少なくなるため、アプローチの効率が低下します。
特に、特定の業種や企業規模に限定される商材では、見込み客のリストを短期間で使い切ってしまい、新規顧客の開拓が難しくなるでしょう。このような企業では、インサイドセールスよりも紹介やリファラルを活用した営業手法の方が適している場合があります。
商品やサービスが高い
高額な商品やサービスは、購入を決断するまでに時間がかかる上により詳細な提案が必要となるため、インサイドセールスだけでは十分な価値訴求が難しくなります。特に、オーダーメイドのソリューションや専門的なコンサルティングサービスの場合、直接営業担当が対面で顧客の課題を深掘りしながら、最適な提案を行う必要があります。
その際、電話やオンライン商談だけではどうしても細かいニュアンスが伝わりにくいものです。そのため、顧客が納得するまでに時間がかかる恐れがあります。フィールドセールスと併用するなど、より効率的かつ効果的な商談の進め方を模索すべきでしょう。
業務縮小の傾向にある
企業の成長戦略によっては、新規顧客の獲得よりも既存顧客の維持に重点を置く方が良い場合があります。特に業務縮小の方針を取っている企業では、新たなリードに大量にアプローチするインサイドセールスの導入は不向きと考えられ、さらにコスト面でも負担が大きくなりがちです。
このような状況ではアプローチの数を増やすよりも、既存顧客との関係を強化し、リピーターやアップセルを促進する施策に注力する方が売上の安定につながるでしょう。
インサイドセールスで成果を出すための3つの工夫

ここまでお読み頂いた方なら、インサイドセールスは適切な戦略と運用が求められる営業手法であるとご理解頂けたかと思います。ただ闇雲に電話やメールを送るだけでは成果につながりません。それでは、インサイドセールスで成果を上げるために抑えておくべき3つのポイントを解説します。
営業ツールを活用して業務効率を上げる
インサイドセールスでは、多くの見込み顧客に迅速かつ的確にアプローチする必要があります。そのためには、営業支援ツール(SFA)や顧客管理システム(CRM)の活用が欠かせません。これらを導入すれば、リードの管理や商談の進捗を可視化でき、業務の効率化が図れます。
また、過去の対応履歴をデータとして蓄積しておけば、将来顧客へアプローチする際に活用し、より良い対応が可能になるでしょう。営業担当者の負担を軽減できるとともに、成約率の向上にもつながります。
トークスクリプトを改善し成約率を向上させる
インサイドセールスでは、顧客の興味を引きつけ、本音を引き出せるようなトークスキルが求められます。そこでやるべきなのが、トークスクリプトの改善です。画一的なセールストークではなく、顧客の業界や立場に応じて最適な話し方を工夫することが大切です。
また、商談の過程で効果的だったフレーズや質問を分析し、スクリプトに反映させることで、営業チーム全体の成約率向上につながります。定期的な見直しを行い、より効果的なコミュニケーションを実現させましょう。
教育体制の整備
インサイドセールスの成功には担当者のスキル向上が欠かせません。特に、顧客の課題を的確に把握した上で適切な提案を行うためには継続的な教育が必要です。具体的には、ロールプレイングによる実践的なトレーニングや、過去の成功事例をもとにした勉強会を実施するなどして、営業力を強化していきましょう。また、新人だけでなく、経験者もスキルを磨き続ける環境を整えることで、チーム全体の成果を最大化させていくべきです。
まとめ
インサイドセールスは、効率的な営業手法として多くの企業で導入が進んでいます。一方で、業務負担の大きさや顧客との信頼関係の構築が難しい点から「やめとけ」と言われてもいます。しかし、売上の安定化や業務の属人化回避などさまざまなメリットを得られるため、一度は導入を検討してみるべきです。そして、導入するからには適切な運用を行いたいですし、そのためには適切なツールの導入が欠かせません。
ツールの導入をお考えになる際は、ぜひBeerfrothをご検討ください。Beerfrothは、インサイドセールスの業務効率化と成果向上をサポートします。他の企業よりも大きな営業力をいち早く手に入れたいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。